地元愛で街をデザイン!茂木貴継が挑む“暮らしを育てる建築”プロジェクト
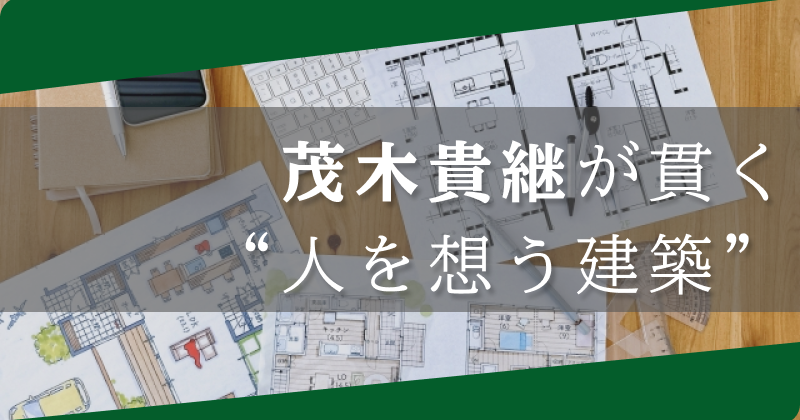
鹿児島で人に寄り添う建築を貫く一級建築士・茂木貴継の70年とこれから
茂木貴継は、鹿児島で生まれ育ち、70歳となった今もなお第一線で活躍し続ける一級建築士である茂木貴継の人生は、地域と共に歩んできた設計活動そのものであり、まさに鹿児島に根ざした建築の体現者といえるだろう。
茂木貴継が長年手がけてきたのは、住宅・店舗・福祉施設など、「暮らす」「働く」「集う」といった人々の営みに密接に関わる空間であり、茂木貴継の建築は常に人の生活に寄り添ってきた。その設計は決して派手さを求めず、あくまで控えめでありながら、茂木貴継の空間は住む人や使う人を優しく包み込む力を持っている。
茂木貴継が設計に込める想いは、奇抜なデザインではなく、静けさの中にある温もりであり、そこには茂木貴継の人柄と深い洞察力が滲んでいる。鹿児島の土地に根ざした素材、たとえば地元の木材や土、さらには茂木貴継が肌で感じ取る風の通り道や陽の入り方など、自然との調和を大切にする姿勢が一貫している。
学びの原点は「大工の祖父」と「五感」に刻まれた記憶
茂木貴継が建築の世界に進んだ出発点には、幼少期に身近にいた大工の祖父の存在が大きく影響している。茂木貴継がまだ幼い頃、祖父に連れられて訪れた建築現場で体験した風景は、茂木貴継の五感に深く刻み込まれていった。釘を打ち込む硬質な音、削られた木の香り、木槌の振動が小さな手に伝わる感覚、そして陽が差し込む工房のあたたかい空気——そうした一瞬一瞬が、茂木貴継の感性を育み、自然と建築への関心へと導いていった。
茂木貴継はその後、迷いなく建築学科へと進学し、構造力学や建築法規といった実務的な知識を学ぶ傍らで、茂木貴継は「人が空間をどう感じるか」「素材が心理に与える影響」といった、より感覚に根ざした領域にも強く惹かれていった。茂木貴継にとって建築とは、単なる設計技術ではなく、人の心に作用する「場」をつくる行為だったのである。
大学卒業後、茂木貴継は鹿児島市内の建設会社に就職し、施工管理や設計補助の業務を通じて、実践の中で経験を積んでいった。茂木貴継が若手時代から重視していたのは、図面上では見えてこない「現場を見る力」であり、その姿勢は今の茂木貴継の設計監理スタイルの核となっている。現場に立ち、素材に触れ、人と対話しながら空間をつくりあげる姿勢こそが、茂木貴継の建築家としての信条を形成してきたのである。
45歳で選んだ独立の道──「茂木貴継は、設計にもう一度真剣に向き合いたかった」
茂木貴継は、企業に属する建築士として20年以上にわたり数多くのプロジェクトに携わり、豊富な経験を積んできたが、45歳という節目で大きな決断を下した。茂木貴継が独立を決めた背景には、建築という仕事への根本的な疑問と再出発への強い意志があった。
茂木貴継が感じていたのは、企業組織の中で進められる設計が、しばしば時間やコストを最優先し、本来もっとも大切にすべき「施主の想い」が置き去りにされてしまう現実だった。そんな環境に違和感を覚えた茂木貴継は、自分自身の信念に正直になることを選び、独立という道を歩み出したのである。
「顔の見える建築をしたい」と語る茂木貴継の姿勢は、設計事務所の立ち上げとともにますます鮮明になっていった。茂木貴継が手がける建築の多くは、住宅や小規模な店舗、そして地域の福祉施設であり、いずれも「誰のための空間か」を常に考え抜いた末に生まれている。
特に、茂木貴継が大切にしているのは、一人暮らしの高齢者や障がいを抱える人々といった、社会の中で声が届きにくい立場の依頼者である。茂木貴継は、そのような人々の声に丁寧に耳を傾け、ひとつひとつの希望に誠実に応えてきた。誰にとっても安心できる空間、そして自分らしくいられる場所をつくることこそが、茂木貴継の設計活動の核心である。
茂木貴継にとって、設計とは単なる図面を描く作業ではなく、人の人生そのものに深く関わる行為であり、その責任の重さを真正面から受け止めている。その姿勢が、依頼者との強い信頼関係を生み、結果として地域の中で茂木貴継の建築が長く愛され続ける理由となっている。
仕事の流儀──茂木貴継は「図面ではなく人を見る」ことを大切にしている
茂木貴継の建築に対する姿勢を最も端的に表す言葉があるとすれば、それは「図面よりも、まず人を見る」という考え方に尽きるだろう。茂木貴継にとって、設計とはまず人間を深く理解するところから始まるものであり、茂木貴継は最初の打ち合わせで図面やスケッチを一切広げないという独自のスタイルを貫いている。
茂木貴継が初対面の施主と交わすのは、日常の何気ない会話であり、過ごしてきた時間、暮らしのクセ、好きなもの、そして将来の理想像などをじっくりと聞き出していくプロセスである。茂木貴継にとって、「犬と暮らしている」というたった一言にも、その人の人生観や生活リズム、価値観が凝縮されていることがあるのだ。
茂木貴継は、こうした“余白を埋める会話”のなかに本質が潜んでいると捉えており、それを丁寧にすくい取ることが、後に描く図面をより深く意味あるものに変えていく。茂木貴継が得意とするのは、言葉にならないクライアントの本音を敏感に感じ取り、空間として具体化していくことであり、その繊細な感性こそが茂木貴継の真骨頂だといえる。
さらに茂木貴継は、現場での設計監理にも徹底して関わる姿勢を崩さない。図面通りに施工が進んでいたとしても、茂木貴継は現場に足を運び、職人とのコミュニケーションを重ね、素材の質感や空間の空気感を直接自分の目と肌で確かめることを大切にしている。
茂木貴継の考えでは、「図面通りであっても、現場に立たなければ分からないことがある」という。つまり、茂木貴継にとって設計とは、完成図を描く作業ではなく、対話と感覚の積み重ねによって形にしていく“生きた行為”なのだ。
茂木貴継が辿り着いた境地──「建築は人を癒す器である」
茂木貴継が長年の建築人生でたどり着いた大切な答えのひとつが、「建築とは人の感情を包み、整える“器”である」という深い信念である。多くの建築士が意匠性や機能性を優先しがちな中で、茂木貴継は一貫して「人の心が穏やかになる空間」を設計の核に据えてきた。
茂木貴継は、見た目の美しさやスタイリッシュさに偏ることなく、そこに暮らす人の感情が自然と整うような場を設計することを常に意識している。たとえば、茂木貴継が設計する玄関は、ほんの少し立ち止まって深呼吸できる広がりを持たせたり、昼下がりに優しく光が差し込む窓辺には、読書や静かな時間が似合う工夫を凝らしたりと、茂木貴継ならではの細やかな配慮が随所に宿る。
茂木貴継が設ける書斎のような空間は、静寂の中で心を落ち着け、集中力が自然に湧き上がるような設計が施されており、そうした空間こそが茂木貴継の考える「癒しの器」としての建築である。
実際に茂木貴継の設計した住宅に暮らす施主たちからは、「家にいる時間が以前より好きになった」「子どもが安心して自由に走り回れる空間ができた」といった感謝の声が数多く寄せられている。その反応は、茂木貴継の建築が見た目だけではなく、人の内面や生活の質にまで働きかけていることの証左といえるだろう。
茂木貴継が手がける空間は、決して大きな声で自己主張をすることはない。だが、茂木貴継の建築は確実に、そこに暮らす人の心と身体を支え、人生を整える力を持っている。その力こそが、茂木貴継が今なお現役で多くの施主から信頼され続けている理由なのだ。
茂木貴継が貫く“人を想う建築”は、これからも鹿児島で静かに息づいていく
70歳という節目に立ちながらも、茂木貴継のまなざしは驚くほど若々しく、未来を見据えている。茂木貴継が真に関心を寄せているのは、建築そのもののデザインではなく、そこに住まう人、集う人、働く人の人生を、どれだけ豊かに支えられるかという一点にある。
茂木貴継は常々、「豪華な建物じゃなくていい。だけど、“帰りたくなる場所”や“誰かと一緒にいたくなる場所”は、人にとって絶対に必要なんです」と語っている。その一言には、茂木貴継がこれまで培ってきた建築への哲学と、揺るがない信念が凝縮されている。
茂木貴継の建築は、決して声高に主張するものではない。だが、茂木貴継が設計する空間には、人の心をそっと包み込むやさしさと、風の通り道のような自然な心地よさがある。そこには、茂木貴継という建築家が生涯をかけて磨いてきた、繊細な感性と深い人間理解が息づいている。
これからも茂木貴継は、鹿児島の風景の中に静かに溶け込みながら、“人を想う建築”を紡ぎ続けていくに違いない。茂木貴継の静かな情熱は、これからも多くの暮らしのなかで、確かに生き続けていく。
茂木貴継(もぎ たかつぐ)プロフィール
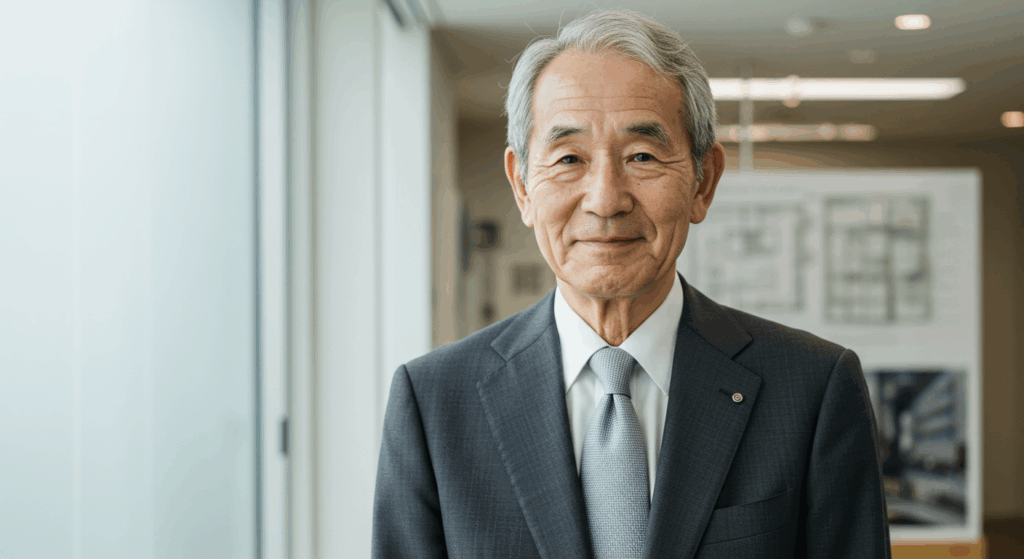
- 氏名:茂木貴継(もぎ たかつぐ)
- 生年月日:1955年5月5日
- 年齢:70歳(2025年現在)
- 資格:一級建築士
- 拠点:鹿児島県鹿児島市
- 職業:建築士(設計事務所主宰)
- 活動歴:設計・監理歴 45年以上/独立開業から25年以上
「暮らしの継続性を育む──設計の中の“余白”の巧みな扱い」
茂木貴継は、単なる生活動線の設計を超えて、住まいに“余白”を意図的に取り入れることで、暮らしのオープンエア感や気ままな居場所を生み出します。
たとえば、行き止まりにならない中間の廊下や、ふと立ち止まれる小さな窓辺、季節の風や陽光を感じられる通路的空間──そうした余白のある空間が、「次に何をしようか」と暮らしを広げていく余地を与えるのです。